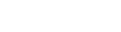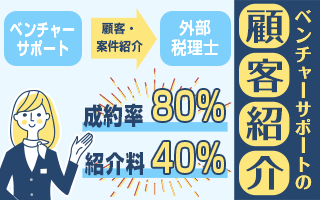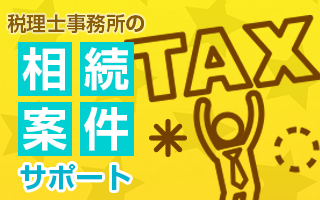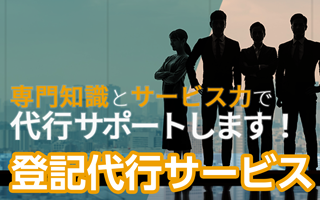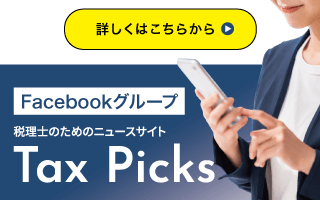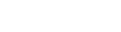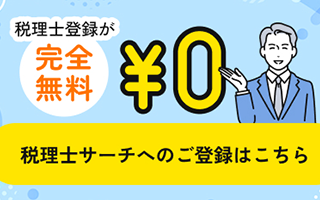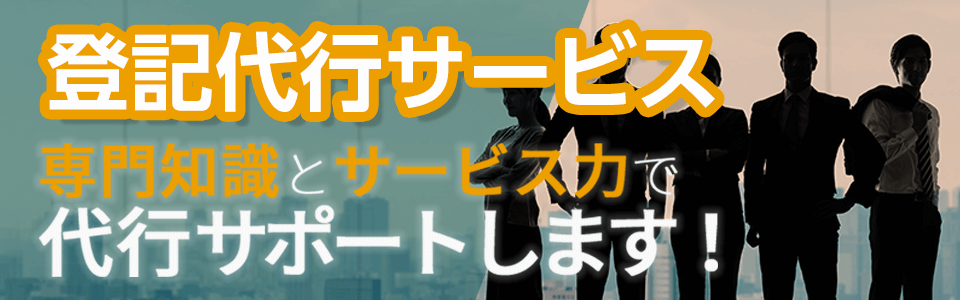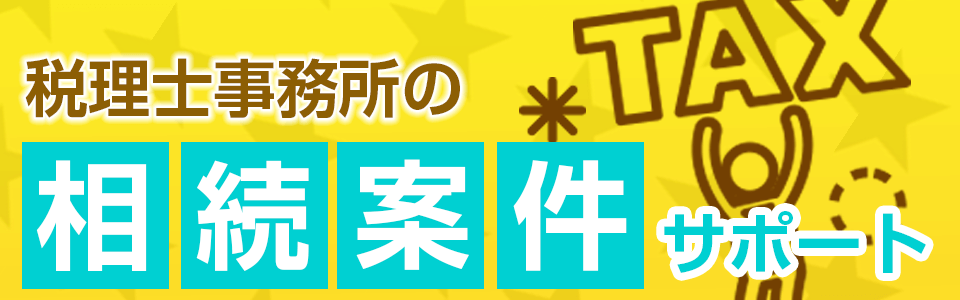株式会社K'sプライベートコンサルティング
公認会計士・税理士 金井先生
毎月の金井先生のKPCレポートです。
今回は、海外の子会社に支払った「業務委託費」が、法人税法上の「寄附金」と認定された平成14年4月26日熊本地裁判決についてわかりやすく解説されています。
全文はこちら 海外の子会社に支払った業務委託費
概略はこちら
事案の概要
食品の製造、販売を行うA社が食品等の貿易業及び販売業等を目的するB社を自社の全額出資で韓国に設立。
なおB社の代表理事にはA社の代表取締役甲が就任し、また現地の従業員2名を雇用。
「経済金融情勢調査、市場需要動向調査、顧客情報等の調査及びA社との間で別途合意した事項」及び毎月100万円の手数料記載の業務委託契約書を締結。
A社は平成9年9月期及び平成10年9月期に、このB社に支払った「業務委託費」計1,500万円を「損金」に算入して法人税等の申告をしたところ、宇土税務署長より「寄附金」と認定され、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分がなされたため、争いに。
B社の実態
B社は、設立後の平成8年末頃から具体的な営業活動を開始しましたが、十分な収益をあげることはできませんでした。例えばB社の平成10年6月期決算を見ると、売上の70%がA社からの業務委託収入であるにもかかわらず、多額の赤字になっていました。
B社の活動
B社の従業員2名の主な仕事は、事務所において電話により得意先から注文を受け、受注した製品をA社に発注し、入荷した製品を受注先へ配送するために運送業者に電話連絡をすること。
またその他の業務も会社運営に関する内部的な事項にすぎず、業務委託契約で定められた「経済金融情勢調査、市場需要動向調査、顧客情報等の調査」などがされた形跡はなかった。
またA社はB社が業務委託契約に基づき「(A社の)広告宣伝活動(を韓国でしている)」と主張し、その具体的な内容として「第11回国際健康産業博覧会」への参加や「雑誌への宣伝広告の掲載」を示しました。しかし熊本地裁はこれらは「(B社)自身の営業活動の一部として行われたと見るのが自然である。」と結論付けました。
結果
原告のBに対する本件支出は、Bが行った役務の対価ではなく、経営状態の悪かったBを維持存続させるための無償の資金供与であったものであり、法37条6項の寄附金に該当するとしました。
さらに熊本地裁は「Bは、原告が全額出資して設立された外国法人であり、租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者に該当するから、同条3項により、寄附金たる本件支出額を原告の損金の額に算入することはできないこととなる。」とし税務当局の主張が全面的に認められました。
まとめ
子会社等であっても、通常の取引先と同じように扱うという感覚を持ちたいところです。次に「報酬の適正性について説明できるようにしておく」ということです。こちらも通常の取引先が相手だと、見積の明細をやたらと細かくチェックしたり、全力でディスカウント交渉をするのに、相手が子会社等だと何となく適当に報酬を決めてしまったという経験のある会社も少なくないのではないでしょうか。とは言うものの、ではいくらが適正な報酬なのかと聞かれると、ハタと困ってしまうところです。色々な仕事があるので一概には言えませんが、例えば子会社に依頼する仕事と同じような仕事をしている大手企業があって、そこが報酬体系や単価を一般公開していればそれを参考にしてみるという方法が一つのアイデアとしてあるでしょう。あるいは業界の専門誌や新聞、書籍などに相場のデータが載っていれば、それを参考にしてみるというのもありではないでしょうか。そのようなものがなければ自社でその仕事をやったと仮定した場合の人件費コストなどを計算し、そこから一定割合をディスカウントした金額としたなどの説明も、計算が合理的に行われていれば有用な説明になると考えます。